
蒼ざめたハイウェイ
じっ実は・・・。
CHEAP TRICKの隠れファンです・・・。ああっついに暴露してしまったぁ。
前身バンドのころはなぜか口が裂けても言えませんでした。(汗)リアルタイムではなく、人気絶頂から少しピークダウンしてきた1983~1984年位(?)に出たアルバムからファンになり、昔のアルバムを揃えていったくちですが・・・。
実は、ヴォーカルのロビン・ザンダーの王子様系ルックスに釣られジャケ買いしてしまったのがきっかけで、動機は不純だったかも。
Heaven Tonight
当時はまだハードロックのハの字も知らん!ヘビメタってだっさ~!などとのたまって、トップ40ばかり聴いていた頃でした。
いま聴き返すと、一番ハードロック色が強いのは、ファーストアルバムの”CHEAP TRICK”で、いまでも好きで一番よく聴きます。
Cheap Trick
ライナーノーツに、THE KINKSやThe Who、BEATLESが好きらしい、と書いてあって、当時はなんのこっちゃ?でしたが、最近やっと少し「ああなるほど!」と思えるようになりました。
ただ、やっぱり彼らの魅力が詰まった一枚と言えば、”In Color”(邦題「蒼ざめたハイウェイ」)でしょうか。
アメリカンハードポップ、と称されることの多い彼らですが、初期は結構、ブリティッシュロック好きがアメリカンR&Rやったらこうなった!みたいな、ちょっと不思議な魅力を持っていました。”I Want You To Want Me “などものすごくポップでキャッチーな曲や、サザンロックを意識した”Southern Girls “にしても、どこかUKの香りがするように感じてしまいます。
ライナーノーツを、大貫憲章さんと渋谷陽一さんが対談で綴っていたのも、今になるとむっちゃツボです。大貫さんの言葉を引用させて頂くと、「CHEAP TRICKの素晴らしさっていうのは、ハード・ロックに対する開き直りみたいなセンスにとどめを指すと思うんだ。従来のハード・ロック・センスではとらえられないものを持っているね。」
自分がハードロック畑に飛び込む前、彼らにどっぷりハマッたのは、凄く貴重な体験だったかも知れませんね。
あまりにもベタベタのヒロイズムに陥ったり、ロックといいながら骨太感がないのは大嫌い!という感覚を持ったのは、常にいたずらっぽい人をくった視点で、骨太なロックンロールを発信する彼らの楽曲に親しんでいたせいかも知れません。
過去に一度、”Clock Strikes Ten“をセッションで演奏できた時は嬉しかったなぁ・・・。
ロビン・ザンダーは、甘いルックスを持っているだけでなく、ヴォーカリストとしての表現力の幅の広さにもずば抜けていると思います。
バラードでは艶のある甘い声で魅了し、ハードなナンバーでは、シャウティングしずっぱりで同じ人?という位の野郎ヴォイスで歌ってみせたり。まだ自分がハードロック歌う様になるとは夢にも思っていないころでしたが、すげ~と思って聴いていた記憶があります。凶暴な声、を出すときはホントにフリでない凶暴な声で表現するのです。それだけ、歌詞の内容にのめりこんで歌っているのだなぁと思います。
ギタリストのリック・ニールセンのエキセントリックなキャラや、遊び心溢れるオリジナルギターも魅力でしたし、ドラムスのバーニー・カルロスはえっサラリーマン?といった風貌でワイシャツにネクタイがトレードマークでタイトなビートを叩き出すし、オリジナルメンバーで12弦ベースを駆使するトム・ピーターソンもすごく耳に残る印象的なベースラインを奏でるし。
(トムは楽曲面での貢献度も高かったらしく、彼の脱退がバンドの人気にかげりが出た原因?という声もあったようです。現在は再加入しているようですが。)
ともあれ、マンガチックなメンバーの風貌の面白さや、楽曲の良さ、ヴォーカルのロビンとベースのトムの甘いルックスも手伝って、”AT BUDOUKAN”というライヴアルバムでまずは本国より日本で大ブレイクすることになります。
Cheap Trick At Budokan: The Complete Concert
“AT BUDOUKAN”は、”In Color”のトップチューンである”Hello There“という2分にも満たないR&Rチューンで幕を開けるのですが、かっこいいんだな、これが・・・。弾いてる、というより暴力的に唸る感じのリックのギターサウンドが、オープニングから一発ガツ~ンとかましてくれる感じで・・・。
冬の時代も長かったようですが、映画「トップガン」の挿入歌などをきっかけにシーンに返り咲き、現代のPOPSのシーンでも頑張っている彼らはやはり凄い!と思います。
これからは隠れファンです、と小さくならず、声を大にしていきたいなぁ。
- 投稿タグ
- 好きなアーティスト



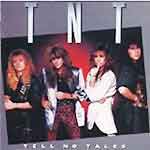
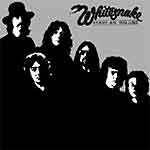

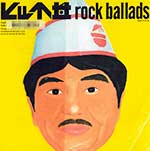
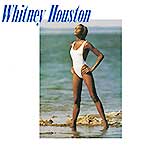

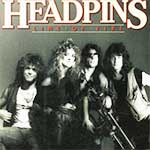
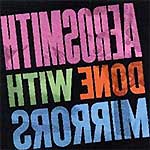
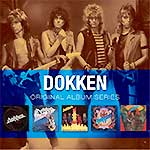
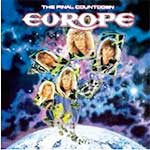
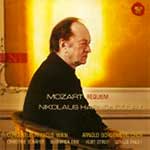
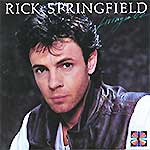
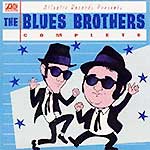

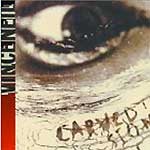
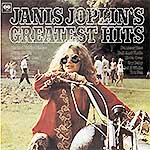
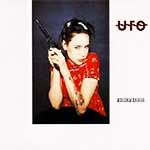
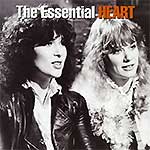
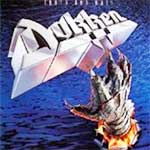
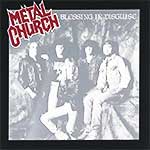

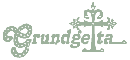
Recent Comment