ヴィンス・ニールのソロアルバム”CARVED IN STONE”を聴きました。
(といっても今日は途中までですが。
いつも新しい音源を聴くときは集中して入り込んで聴いてしまいますので、「ながら聴き」ができないのが悩みでして・・・。)
スティーヴ・スティーヴンスと組んで出したアルバム、という予備知識がありましたので、ビリー・アイドル調のイケイケ(これも死語?)なハードロックを想像していました。
でも実際は、当時流行った重たいリフ重視のヘヴィロックのスタイルを借りながら、ダークでシリアスな作風と感じました。
自分はモトリー・クルーのファンとはおこがましくも言えません。あくまでMTVでオンエアされていた曲ばかりが記憶に残っている位しか聴きこんでおらずお恥ずかしい限りですが、”Home Sweet Home”や”You’re All I Need”などのバラードは大好きでした。
なぜかCHEAP TRICKのロビン・ザンダーと共通するような、明るく甘い声質をヴィンスに感じたのと、素直にロングトーンを伸ばしたときの声の感じが好きだったのです。バラードを聴いて、この人、いい歌を歌うヴォーカリストなんだと改めてしみじみ思ったりしてました。
ただこのソロアルバムを聴いて、なぜか初めてヴィンスの内面をみたような気がしました。
当時アメリカでもっとも成功したバンドの一つだったモトリーですが、売れ続けるために、常にコマーシャルであり続けることを、大きなプレッシャーとして感じていたのかも知れません。
ダークな曲調の中でモトリー時代よりむしろ淡々と歌い上げるヴィンスの声には、不思議な魅力がありました。
スティーヴ・スティーヴンスのリフや乾いた音色もさることながら、起承転結でむりやり盛り上げようとしないストイックな曲調、コードワークなどを聴いているうち、とあるイギリスのバンド、KILLING JOKEを思い出してしまいました。
KILLING JOKEは昔好きでよく聴いていました。彼らはもともとポジティヴ・パンクといわれるジャンルにわけられていたような・・・初期はかなりパンキッシュで、UKロックのストイックなほの暗い感じが、アメリカの産業ロックになじんでいる自分には逆に新鮮でした。その彼らが後期、曲調やUKパンク独特のコードワークを残したまま、ハードロックに近いサウンドで演奏した時期があったのです。
外交に向かうのでなく、内面に向かう音楽。そのほの暗さと神秘性は、他のハードロックバンドにはない魅力でした。
特に5曲目の、”Writing On The Wall”で、それを強く感じました。
アメリカン・ロックンロールのシンボルまで上り詰めたヴィンスが、実はこういうサウンドで自分を表現したかったんだと思いました。スティーヴ・スティーヴンスも、自分が固定観念で決め付けていたギタースタイルと異なって、とても魅力的なギターを弾く人だったんだと、改めておもった次第です。
残りの曲も、明日じっくり聴いてみようと思いました。
- 投稿タグ
- 好きなアーティスト
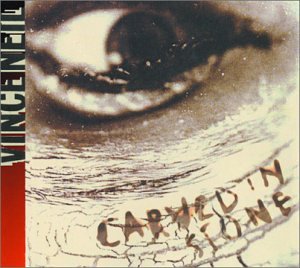






















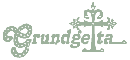
コメント